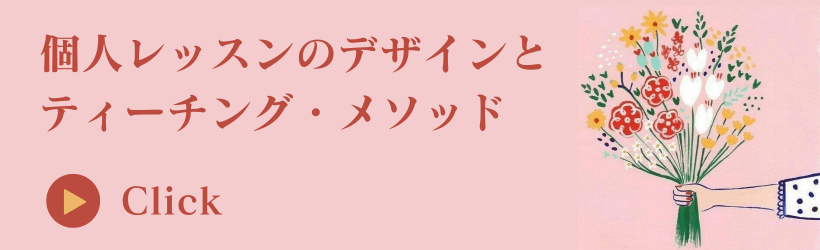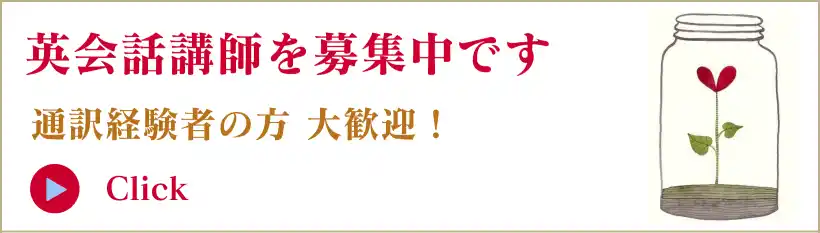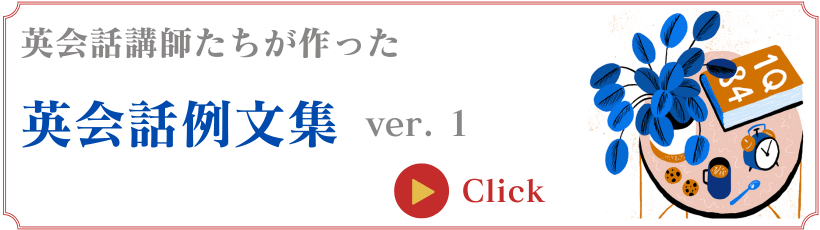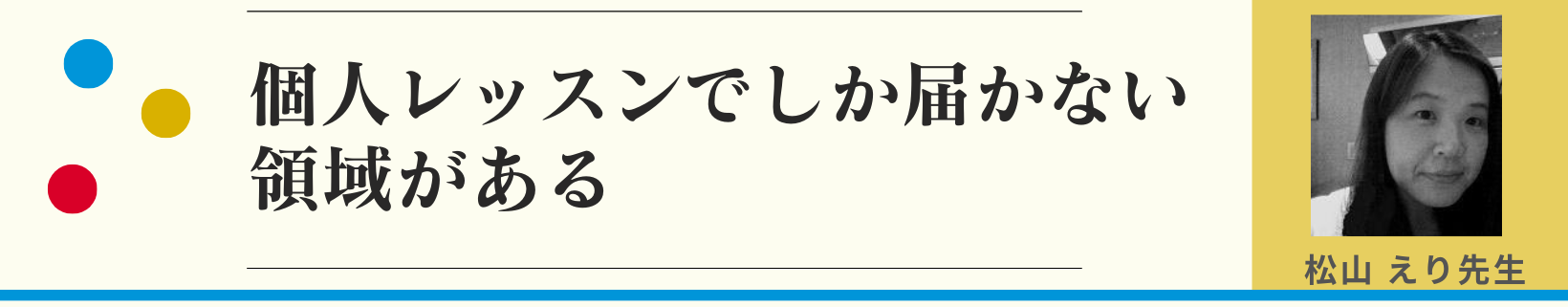
松山 えり先生 33才
- アメリカ フロリダ州オーランドの州立大学で心理学を専攻。
- 卒業後、外資系貿易商社に入社。 翻訳業務を担当。
- 5年前、結婚を機に MyPace English での英会話先生の仕事を開始。
- 6才の女の子から、40代のご夫婦まで、8名さまの英会話マンツーマンレッスンを担当。
- フリーランスの翻訳者としても活躍中。
上達を支える マンツーマン英会話の 戦術・戦略
『実技を通して習得するのが英会話は * 流動性知能。 英文法の知識を積み重ね、英単語の暗記作業から 語彙を獲得していく 英語学習は * 結晶性知能。 長期記憶や意味記憶(結晶性知能)を、どのように 流動性知能に昇華させるのか? ここに 英会話上達のヒントがあるように 思えます。 そして 抽象的であったヒントや 直感的なひらめき を、アウトプット・トレーニングという 具体的なメソッドに 落とし込むことで、演習効果が高まる。 この上達の過程を踏むためには、マンツーマン英会話 が もっとも 理に適った手法を導入しやすい 指導方法であると 思います。』
『昨今 "日本の英語教育の根本的な誤りは..." と題した教育関連の討論が 盛んに行われています。 ただ もっと正確に 言えば "学校で獲得した 英語知識だけでは 不十分である。 英語スピーキングには 潜在意識を用いた 言語操作能力を磨くトレーニング(自動運転モード)が必要であるが、中学・高校の6年間という 短い期間で 顕著な学習成果を スピーキングの分野で 出すことは 不可能かもしれない。" と言い換えられると思います。』
『英文法の演習ドリルの スコアが上がっても、英語が話せるようにはならない - 直感的な言語操作力を養うためには 学校の英語授業とは 異なる学習アプローチが不可欠です。 英語音声で質問を聞き取り、英語で返答する 一連の情報処理のスピードと 正確、運動性言語野(* ブローカ野) の働きを意識した 演習を繰り返し行うことにより、パターン認識能力を高めることが必須の課題ですし、流暢性を重視したプログラムが望まれます。』という松山えり先生。 英会話 上達のヒントについて伺ってみました。
* ブローカ野: 左前頭葉に位置するブローカ野は、統語・文法処理に関わる "言葉を話す" ための役割を果たします。 一方 ウェルニッケ野は "言葉を聞く" ために必要な脳部位といわれています。
マンツーマン英会話では "話す" に比重を置く
『英会話 マンツーマンレッスンでは インプット・プロセスと アウトプット・プロセスを 分けて考えます。 音は具象で、思考は抽象なため、分けて考えた方が、より 深い内容を話し合うことができますし、リスニング(ブローカ野)と、スピーキング(ウェルニッケ野)では 用いる脳の部位が異なるため、2つについて同時に話すと 話しが複雑になってしまうことも理由の一つです。』
マンツーマンレッスンでは アウトプット(スピーキング)を中軸に 授業は展開します。 具体的には 生徒さまに クローズエンドの質問を出し (Yes, No で答える質問)、文脈の共有を確認した後、オープンエンドの質問(How や Why で質問し、自由に英語で返答してもらう)を出し、返答で受け取った オーラルの英語を 精査していきます。 チェックのポイントは 英文法、発音、意味の正確性、ニュアンス、文脈の流れ ですが、それらを訂正・調整し、伝わりにくい箇所を指摘したり、もっと英語らしい表現法を提示し、アウトプットに 組み込んでいく。 そうすることで、アウトプット全体の 複雑性 (Complexity)、正確性 (Accuracy)、流暢性 (Fluency) が改善され、日本語 - 英語の直訳型の表現から、シンプルでも漏れの無い、長くても ダブりのない、英語らしい表現に 近づいていくのです。』
『一部のオンライン英会話業者は "とにかく 英語で たくさん話すこと" をモットーとしているようですが、それでは スポーツで言う 粗形態に陥って 悪い癖が定着してしまい、洗練された技巧が身に付かなくなってしまいます。 確かに 発話の量も必要ですが、質の低いアウトプットを繰り返しても、上達できないという点は スポーツと同じです。』
リスニング学習に 認知言語学の知見を取り入れる
『MyPace English のマンツーマン英会話レッスンでは リスニング演習と 発音矯正を 同時に行う機会が 多くあります。 "自分が正しく 発音できる音は、聞き取ることができる = 正しい 音素や音節が 音韻貯蔵庫に 記憶されている" と考えます。 これは "言語学上のモータースキルの仮説" に基づく 解釈で、実際 リスニング力の高い学習者は 比例するように 発音も正確です。』
『最近 聞こえてくる英語と全く同じ発音・スピードで繰り返す "シャドーイング" という 通訳トレーニング法の メソッドを取り入れた リスニング学習が話題になっています。 リスニングの学習習慣を作ることは とてもよいことですが、自分の英語発音を 音素、音節から見直し、英語特有の強勢拍リズムを 身に付けないと、聞こえない音の部分は 何回聞いても分からない状態が続いてしまいます。 弁別閾を超えた 音色の相違を識別するためには、やはり 発音矯正のワークが必要になると思います。』
マンツーマン英会話で 柔軟な英語操作力を身に付けよう
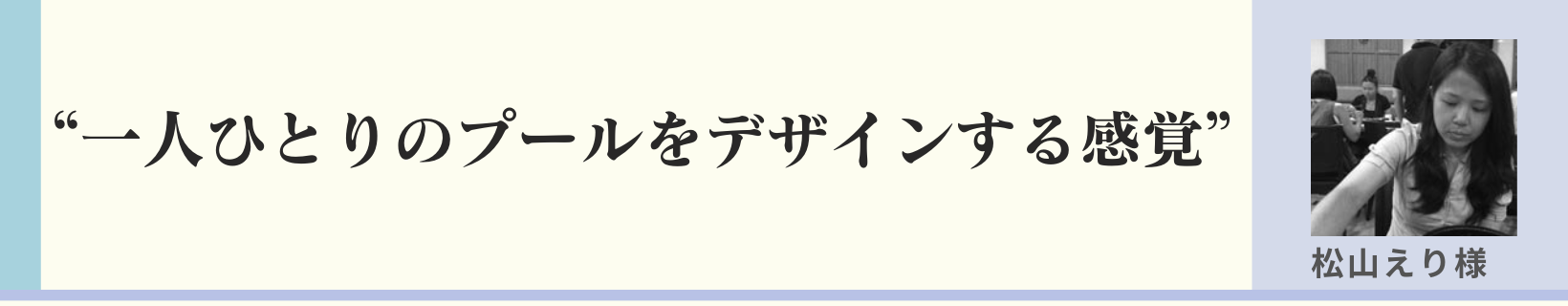
『英語操作力とは頭で考えたことを、英語に反応させて 発話する、一連の能力のこと。 どこに滞りが生じるのか? うまくいかない箇所には、必ず上達のヒントが隠れている。 そこを可動するように整えることで、英語感性に磨きをかけます。 学校の英語試験では、英文法多肢選択問題で誤答選択肢を判定する技量が問われますが、それらのギミックは 英会話の現場では 役に立たない。 知識を蓄えるより、むしろ * 🔗 アンラーニング (学習棄却)を取り入れる姿勢の方が 有効であると思います。』
"先生は教え、受講者は教えられる。" という一方的さがないのが マンツーマン英会話。効果が早い時期に期待できるのは、むしろ初心者の方と松山先生は言います。 『初心者の方には、英語という広い海でいきなり泳ぐのではなく、背の立つプールを用意するという感覚が大切です。 だんだんプールを広く、深くしていけばよい。 みなさん、ある時ぽんと浮上してますよ。』
『例えば初心者の方にとって、"映画を字幕なしで見る。" というのは、ビジョン(理想)であって、現実味のあるステップではありません。 "海外旅行で不自由しない英語力" であれば、だれにとっても手の届く目標となるはず。 理にかなう順番で、一歩ずつ進むことが大切です。』
英会話学習での アンラーニングの重要性
今までの常識が非常識になる * VUCA(ブーカ)と呼ばれる 時代にある現在。 英会話の学習方略に関しても、今までの常識をもう一度見直し、新しい学習法や 教授メソッドを取り入れる必要があると思います。 小学校で英語教育の強化が図られている一方、「小6の約3割が英語嫌いに (産経新聞 17.05.22)」や、「TOEIC高得点なのに英語が話せない (ダイヤモンドオンライン 24.02.25)」 など、英語学習に対する関心が上がるにつれて、新たな学習課題が 浮かび上がっている。 インプット偏重型の学習を "常識" と考える学習者に対し、「英会話では "暗記量を増やすより、思い出すスピードの方が大切"」など 新たな 学習コンセプトを 英会話講師たちは 伝えるべきであると思います。
* VUCA(ブーカ): Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉で、これまでの常識や成功パターンが通用しなくなりつつある 現代の不確実性 を言い表します。
中学・高校の英語の授業では、意味暗記を繰り返し 知識を系統学習の定めた順番に沿ってインプットする。 そして試験では 消去法や 取捨選択により 答え をアウトプットし、エラー発生率の低い人が 立派な成績を上げる という一律のルールで、その知識量を競ってきました。
ただ、試験で高得点をおさめても、海外で英語が通じない、聞き取れないと 感じる人が多い。 試験という 評価基準 (Metrics)に偏りがあるため、試験のガイドラインに従って勉強すればする程、偏りが生じてしまうのが、英語教育の現状ではないでしょうか? 試験の結果や スコア、回答の正誤に 捉われるのでなく、一度 ゼロベースに戻って 初めから 考え直してみよう。 それが私たちの提供する マンツーマン英会話の原点ですし、"アンラーニング" の概念を重要視する姿勢も ここから派生しています。
アンラーニング(unlearning)は 日本語に訳すと "学習棄却"で、古い情報や概念、価値観を一度意識的に忘却し、新しい知識を収集し、新しいアイデアを基に、スキル習得を試みることを 意味します。
私たちの マンツーマン英会話が他の 英会話スクールと異なるのは、「* 学校の英語は 顕在意識(遅くて深い思考)を用いるのに対し、実践的な英会話は 潜在意識(早くて浅い思考)を利用する。 英語の情報処理の際 使う回路が違うのだから 指導メソッドも異なるはず。」というコアビリーフに沿って レッスン内容をデザインしている点にあると思います。
* この概念は ノーベル賞を受賞した 認知心理学者 ダニエル・カーネマンの著書 "ファスト&スロー" から 大きなヒントを得たものです。
6年以上お世話になった 学校英語 の内容が 間違っているということではありません。 英語と英会話では 使用する 情報処理回路が異なるので、学習法と指導法も異なるのです。 そして この新たな視点を持つことで 新たな学習法のヒントが 視界に入ってくるようになるのです。
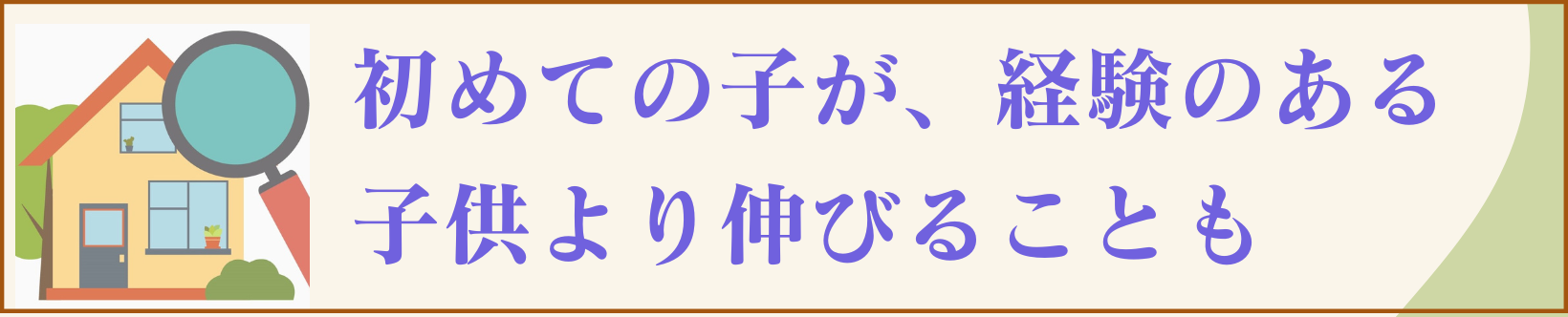
潜在能力を活性化させるキッズ英会話
『5才と、7才の子では、進行が異なりますし、女の子の方が成長の早い、男の子の方が文字に関心が高いなど、個人差・年令差に対し、十分な配慮がなされていない。 そんな子供英会話が、多いように思えます。 例えば 子どもの特性も 成人と同様、視覚優位、言語優位、聴覚優位に分類できると思います。 言語優位の子どもは 英語の聞き取りで混乱することもありますが、授業に音韻符号化や ディクテーションなど、音とアルファベットを結びつけた 演習を行うと 大人でさえ驚くほどの才能を発揮することもあります。』
『また 英単語を何個知っているかという 認知能力よりも、想像力に対する開放性や、自制心など 心の安定性など 数値化できない 非認知能力の成長も評価する "心のゆとり" が 私たち大人にも必要なのだと思います。』
子供たちが大好きな松山先生。 それでも、昨今の子供英会話ブームには、疑問を抱いている様子です。 『"遊びながら、自然に、楽しく。"
という子供英語教室もありますが、そこに大人たちの甘さが、見え隠れする気がします。 子どもは 集中する行為に多大なエネルギを消費するため、子どもにとって 長時間集中することは易しいことではありません。 そのため 講師は 集中に必要な認知資源を 長持ちさせるために、集中と拡散を繰り返す必要があるのですが、一般的な子ども向け英語教室では、この点を重要視せず、"拡散 = お遊び" ばかりを繰り返すため、学習効果が薄いのだと思います。』
『子供たちが英語を学ぶには、まず集中力を発揮する術を知ることが大切です。 脱線しそうな時は、こちらに手を引っ張る意気込み。 それがあれば、どんな子供も必ずついてきてくれます。そして、ご父兄さまと連携し、実を結ぶ環境を作ることも必要です。』
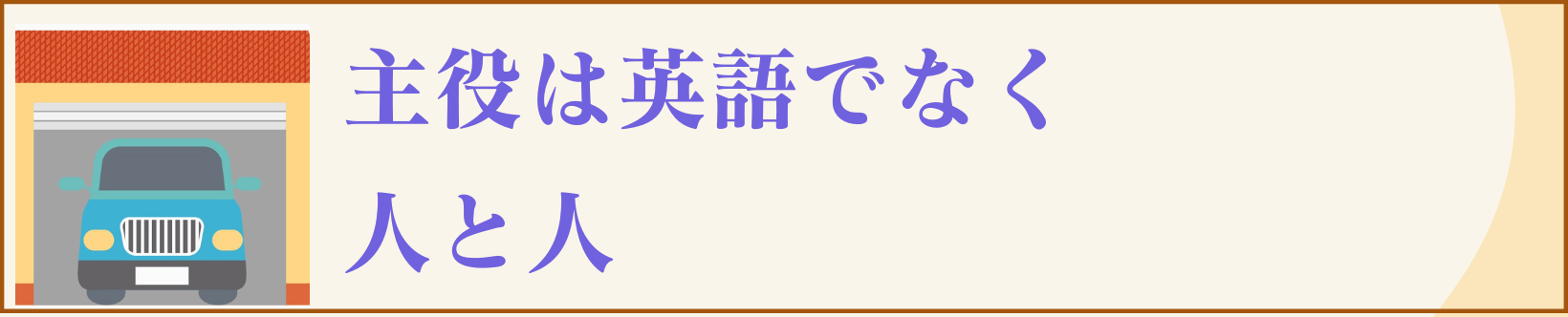
マンツーマン英会話 - 向き合うエネルギーから 発想が生まれる
英会話先生は、担当制が基本。 担当制を採らない英会話スクールもあるようですが、それはマス・カスタマイゼーションの域を超えない マニュアル然としたものでしょう。
『人と人が * 1.2m隔て、1時間向き合う マンツーマン英会話。 喜び、不安、焦り、どんな感情も伝わってしまう距離での真剣勝負です。 非科学的ですが、よいレッスンには必ず、 "あうんの呼吸" が流れています。』 先生がパーソナル・トレーナーとして、いろいろな手段を講じて、その人に一番ふさわしい道のりを一緒に歩んでいく。 それがマンツーマン 英会話。 そこからしか生まれない、密度、細やかさで英語力を活性します。
* 1.2m の距離感は パーソナル・ディスタンスと呼ばれ、友人や親しい人の間で取られる間隔でもあります。 主に言語でのコミュニケーションを前提とし、相手の表情が読み取れる距離であるため、教室という空間でよりも、言語での細かなニュアンスがより伝わりやすくなります。

国際社会の最前線に立とうとする人から、無味乾燥なオンライン英会話に見切りをつけた人、そして 子供の成長を英会話学習を通し 講師と分かち合う ご父兄さままで。 自分にジャストフィットする マンツーマン英会話を 見つけた人たちの 声を集めました。
『英会話を習い始めて 気づいたこと。 それは 英会話は文法が難しいのではなく、日本語と英語の感覚が違いすぎて、変換しにくいということ。 日本語の意味内容(概念)が強く記憶されていて、英単語の語根や語源とずれが生じているのです。 変換しなくてよい方法はあるの? 先生はそのヒントを知っているはず。 余計に知りたくなる。』 - 渋谷 真由美 様 (目黒区 祐天寺)🔗 ラスベガスで活かす - トラベル英会話
『ビジネス・パーソンとしての目線を軸に、自分の英語を再編成しています。 相手の気持ちに配慮してフレーズを選ぶこと。 そして、クロージングには 意識的に強い意味を持つ動詞を用い、コミットメントの意志を表示します。』- 黒木 千絵様 (世田谷区 成城) 🔗 海外出張の準備 - ビジネス英会話
『自宅で リロ & スティッチ のDVD を 家族3人で観ていたら、この島に行きたいと、長男が言いだして。 調べてみると、"庭園の島"と呼ばれる カウアイ島には 他ではみられない豊かな自然が残っている。 そして 雨の少ないところに 由緒あるゴルフコースがあるらしいんですよ。 次の家族旅行は この島がいいねと 妻と話しをしているところです』 - 野澤 祐二様 (千代田区 麹町) 🔗 ファミリーで始める英会話

"先生は難しい単語を使わずに、長時間英語で話しをすることができるのは何故?" その質問のヒントは、講師たちが持ち寄ったフレーズを集めた 🔗 英会話例文集 にあります。 ぜひ 見てみてください。